- はじめに
- なぜ築古アパート投資は難しいのか
- チェックリスト20選【実際の購入経験から厳選】
- ① 土地の路線価と実勢価格を比較する
- ② 再建築の可否(都市計画・接道義務)
- ③ 建物の構造(RC/S造/軽量鉄骨/木造)
- ④ 築年数と法定耐用年数の関係
- ⑤ 積算価格と実勢価格の乖離を確認
- ⑥ 過去の修繕履歴と修繕計画
- ⑦ 雨漏り・白蟻・基礎クラックなど瑕疵の有無
- ⑧ 周辺環境チェック(嫌悪施設・夜の様子)
- ⑨ ライフライン(浄化槽・ガス・給排水の種類)
- ⑩ 現在の入居率と空室の理由
- ⑪ 募集家賃とレントロールの妥当性
- ⑫ 管理費・固定資産税・火災保険などのランニングコスト
- ⑬ 外壁・屋根など大規模修繕の見込み
- ⑭ 足場の必要性と費用(高さ・隣接状況)
- ⑮ 駐車場・駐輪場・ゴミ置き場の整備状況
- ⑯ 金融機関ごとの融資条件(法人・個人の違い含む)
- ⑰ 減価償却と融資期間への影響
- ⑱ 周辺の家賃相場とのギャップ
- ⑲ 出口戦略(売却・分割・戸建転用)を考えておく
- ⑳ 買い付け・交渉時の戦略を明確にする
- まとめ|築古アパートは“準備力”がすべて
はじめに
築古アパート投資は「高利回り=儲かる」と思われがちですが、実際には見えない落とし穴がたくさんあります。
私自身、複数の築古物件を検討・内見し、金融機関に融資打診を重ねる中で「これは事前にチェックしておかないと危険だ」と痛感したポイントが山ほどあります。
この記事では、不動産投資を始めたばかりの40代サラリーマンである私が、現地調査・積算評価・入居率・融資条件など、プロの目線で整理した20項目のチェックリストを紹介します。
一つひとつ丁寧に見ていけば、築古アパートでも「失敗しにくい投資」が可能になります。
なぜ築古アパート投資は難しいのか
高利回りの裏に潜むリスク
築古アパートは新築に比べて価格が安く、利回りも高く見えることが多いです。
ですが、それは見た目の数字に過ぎない場合もあります。
修繕費・空室リスク・築古特有の融資制限など、初心者が見落としやすいリスクが山積みです。
たとえば、利回り12%と書かれていても「その家賃、実際に埋まるのか?」「入居者層は誰か?」といった検証が抜けていると、フタを開けてみれば赤字になることも。
情報非対称性とスピード勝負の世界
特に築古物件は「情報が早い者勝ち」であり、業者の言いなりになって動くと不利になります。
マイソク(物件資料)だけでは判断できない情報が多いため、現地調査と事前準備が何よりも重要です。
チェックリスト20選【実際の購入経験から厳選】
① 土地の路線価と実勢価格を比較する
路線価は積算評価のベースになります。不動産ポータルでは実勢価格(相場)しか分からないため、国税庁の路線価図から確認を。実勢価格>路線価なら、資産価値の下支えが弱い可能性も。
② 再建築の可否(都市計画・接道義務)
特に旗竿地・私道・2項道路の物件は要注意。「再建築不可」だと将来的な売却に大きな影響が出ます。不動産屋に任せず、自分でも役所で都市計画・建築指導課を確認しましょう。
③ 建物の構造(RC/S造/軽量鉄骨/木造)
構造によって修繕コストも融資条件も異なります。
- RC(鉄筋コンクリート)→長寿命だが修繕費高
- S造(鉄骨)→耐久性あり
- 木造→DIY向きだが融資年数が短くなる傾向
④ 築年数と法定耐用年数の関係
築30年を超えると、木造なら耐用年数がほぼゼロ。融資期間が短くなり、返済額が上がります。築年数×構造で耐用年数を逆算し、融資可能な年数を見積もりましょう。
⑤ 積算価格と実勢価格の乖離を確認
積算が物件価格に対してどれくらいあるかが、金融機関の評価に直結します。
- 土地:路線価 × 面積
- 建物:再調達価額 × 延床面積 × 残存年数割合
積算<価格なら指値交渉の余地アリ。
⑥ 過去の修繕履歴と修繕計画
「前回屋根いつ塗装した?」「給湯器は何年前?」など、売主や仲介に確認。履歴がない場合は、それだけで数百万のリスク。マイソクに書かれている内容だけでは不十分です。
⑦ 雨漏り・白蟻・基礎クラックなど瑕疵の有無
目視だけでなく、床下・天井裏を覗ける機会があれば必ずチェック。白蟻保証や調査記録があれば安心材料に。専門家によるホームインスペクションも検討の価値あり。
⑧ 周辺環境チェック(嫌悪施設・夜の様子)
昼間に良く見えても、夜はガラが悪い地域もあります。
- ゴミ置き場の汚さ
- コンビニのたまり場化
- 飲み屋・パチンコの距離
など、現地に足を運ばないと分からない要素が多いです。
⑨ ライフライン(浄化槽・ガス・給排水の種類)
・浄化槽だと維持費が高くなる
・プロパンガスは家賃に転嫁しづらい
・単独浄化槽や井戸水など、古い設備だとトラブルの元。管理会社にも相談して判断を。
⑩ 現在の入居率と空室の理由
空室がある場合は「なぜ空いているか?」の仮説を持つことが重要。賃貸需要の少なさ、設備が古すぎる、近隣にライバル物件があるなど。空室が慢性化している物件は要注意です。
⑪ 募集家賃とレントロールの妥当性
レントロールが現実離れした家賃になっているケースは多々あります。実際に現在募集されている価格(SUUMO・ホームズ)と比較し、現実的な想定家賃で利回り計算を。
⑫ 管理費・固定資産税・火災保険などのランニングコスト
表面利回りではなく、実質利回りを出すために必要な項目。
- 管理費
- 固定資産税
- 火災・地震保険
- 退去時の原状回復費用
これらを合算して、初めてキャッシュフローが見えてきます。
⑬ 外壁・屋根など大規模修繕の見込み
築30年を超える物件は、近いうちに大規模修繕が必要になることが多いです。
特に4階建以上は足場代だけで高額になるため、軽視できません。
⑭ 足場の必要性と費用(高さ・隣接状況)
3階建て以上や隣家と密接している場合は、足場を組むのが困難かつ高額です。施工可能か、近隣からクレームが出ないかなど、管理会社や職人への事前相談も大切です。
⑮ 駐車場・駐輪場・ゴミ置き場の整備状況
これらの設備がなかったり、共用部分の管理が杜撰だったりすると、空室リスクが上がります。家賃のわりに住環境が悪く、結果として入居期間が短くなる傾向も。
⑯ 金融機関ごとの融資条件(法人・個人の違い含む)
同じ物件でも、銀行によって評価・金利・融資割合が異なります。
- 地銀・信金:地場物件に強い
- ノンバンク:金利高いが柔軟
- 法人融資可否や代表者保証の有無も確認しましょう。
融資は銀行側と仲介側のタイミングが合わないと意外なトラブルに見舞われることもありますので、注意が必要です。
【失敗談】郊外アパート投資で買えなかったのに12万円の請求?|築古投資のリアルな落とし穴
⑰ 減価償却と融資期間への影響
減価償却が早く終わる物件は、節税効果が一時的なものに留まります。法人化していない場合、減価償却の使い方次第で、手残りキャッシュが大きく変わるので要注意。
⑱ 周辺の家賃相場とのギャップ
相場より明らかに高い家賃設定は、空室が埋まらないフラグ。SUUMOやat-homeで実際の募集価格をリサーチし、「この設備でこの家賃は無理がある」と思ったら再検討を。
⑲ 出口戦略(売却・分割・戸建転用)を考えておく
将来的に売るのか、住居に転用するのかで、物件選定の基準が変わります。小規模アパートは「戸建化」できる構造かどうかが、出口の柔軟性につながります。
⑳ 買い付け・交渉時の戦略を明確にする
指値をどこまで入れるか、他の投資家に先を越されないためのスピード感、融資承認までの見通しなど、「買うと決めたら一気に進める」準備が必要です。
まとめ|築古アパートは“準備力”がすべて
築古アパート投資は、表面利回りの高さに惹かれて飛び込むと、「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクが非常に高いジャンルです。
物件価格が安いとはいえ、数百万〜数千万円の買い物。
現地調査や金融機関との交渉、見えない修繕リスクなど、確認すべきポイントは多岐にわたります。
今回ご紹介した20のチェックリストを活用すれば、「買ってから失敗に気づく」という事態を大きく減らせるはずです。
私自身も、1つ1つの項目を見落とさないよう、常にマイチェックリストとして活用しています。
そして何より大事なのは、自分の目で見ること、自分の頭で考えること。仲介や業者の言葉を鵜呑みにせず、冷静に判断していく姿勢が築古投資では最も重要です。
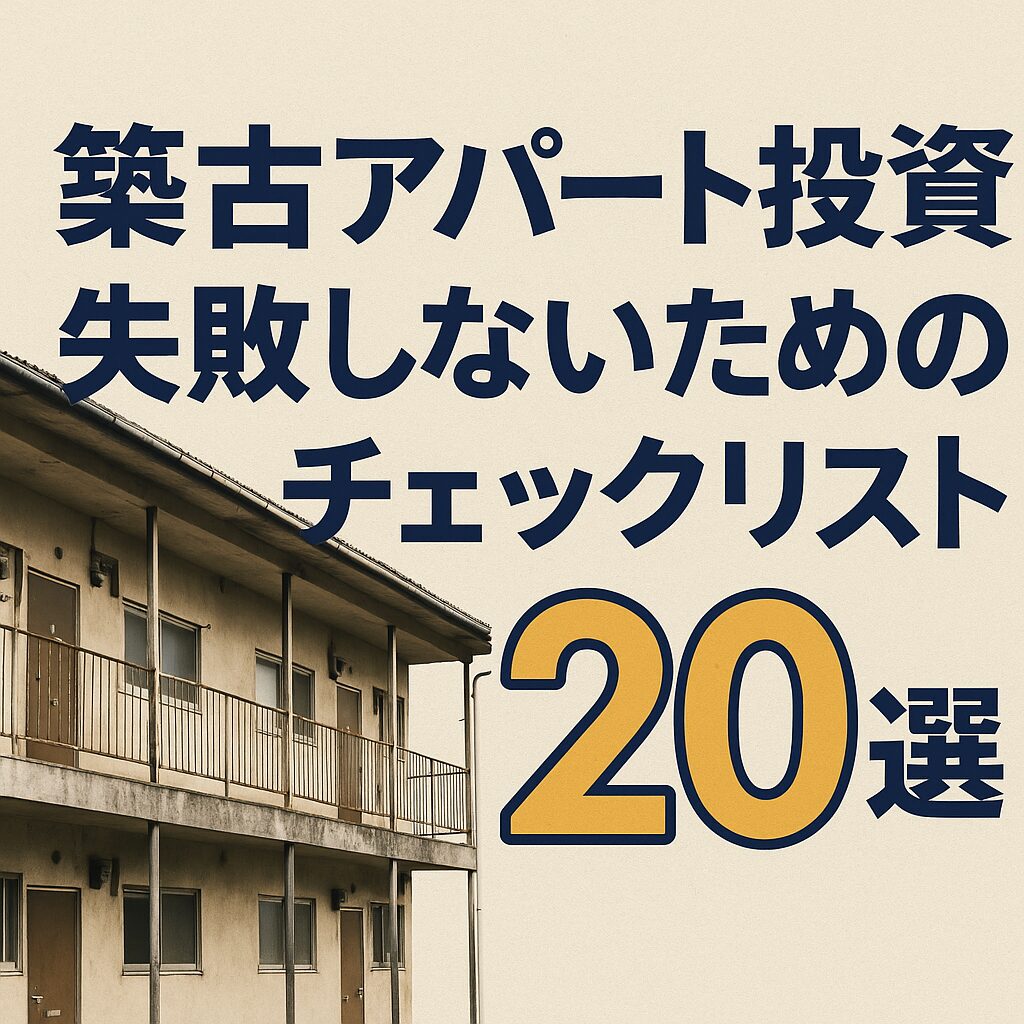


コメント